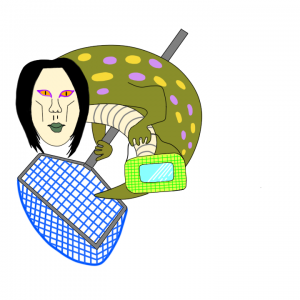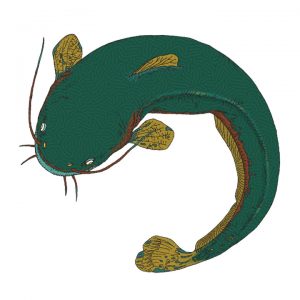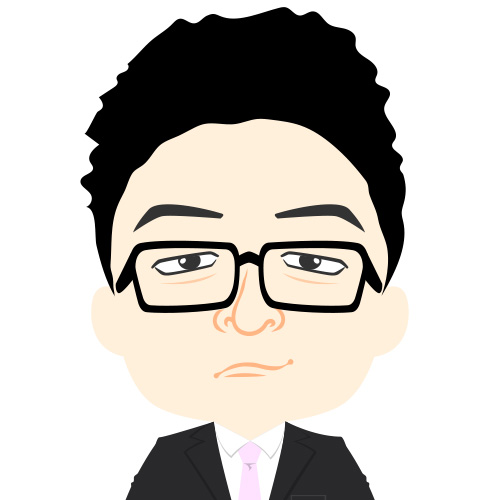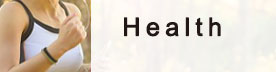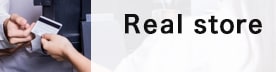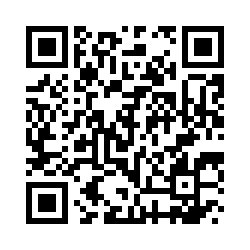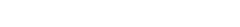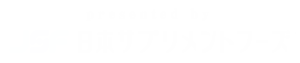【大名店】閉店のお知らせ
目次
最近、何かと話題の「昆虫食」。世界の昆虫食市場は年々拡大しており、2025年には1,000億円規模になる[※1]といわれています。食に困ることのない今の時代に、どうしてわざわざ虫を食べるのか、そもそも虫は安全な食べ物なのかと疑問に思う方は多いのではないでしょうか。そこで、今回は昆虫食のメリット・デメリットに関するお話をさせて頂きたいと思います。
昆虫食のメリット
2013年に国際連合食糧農業機関(FAO)が公表した「食品及び飼料における昆虫類の役割に注目した報告書」[※2]にも記載されているように、昆虫食は動物性タンパク質の配給源として飼育変換率に優れ、環境負荷が少ないといったメリットがあります。具体的にどういったものなのか、1つずつ見ていきましょう。
少ない飼料で育ち、可食部位も多い

飼育交換率とは1kgの収穫を得るために必要な飼料を示す数値で、変温動物である昆虫はこの飼育交換率が非常に高いです。牛とコオロギで比較すると、コオロギが50%(1kg収穫するために2kgの飼料が必要)なのに対して、牛は12.5%(牛の体重を1kg増やすために8kgの飼料が必要)と大きな差があります。[※3]水だけで見ても、牛肉1kg生産するのには20,000ℓの水が必要ですが、コオロギはわずか8ℓの水で同量の収穫が見込めます。[※4]また、昆虫はその大半が可食部位(食べられる部位)ですが、牛の可食部位は40%程度と少ないです。可食部位を踏まえて飼育交換率を計算すると、コオロギは変わらず50%なのに対し、牛は4%(1kg収穫するために25kgの飼料が必要)とさらに大きく差が開きます。
世代交代が早い

食肉として飼育された牛が出荷されるのは約28ヵ月齢(2年4ヵ月)前後で、その体重は約720kg程度[※6]です。そのうち可食部位が40%程度なので、2年4ヵ月で約288kg分を出荷できる計算になります。これに対してコオロギは、50×44×20.5cmの空間で50対の成虫を飼育すると、32日後から毎日6,000匹のコオロギが出荷できるようになります。[※7]コオロギ1匹あたりの重さには個体差がありますので、仮に1匹0.1gとして牛と同期間飼育すると、約484kg分のコオロギを出荷できることになります。これは牛の可食部位で見た出荷量の1.7倍です。同じ広さの空間で飼育すれば、その差はさらに大きく広がります。
栄養が豊富

昆虫は食肉(牛・豚・鶏)や魚と同様に栄養価の高い食材です。昆虫の多くが不飽和脂肪酸とタンパクを豊富に含み、カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルも豊富です。近年は代替肉として大豆も注目を集めていますが、大豆から得られるのが植物性タンパク質に対し、昆虫から得られるのは必須アミノ酸であるBCAA(バリン、ロイシン、イソロイシン)を含む動物性タンパク質です。1匹の重量が軽い昆虫から十分な栄養素を摂取するには大量の昆虫を食べる必要が出てきますが、近年では粉末にした昆虫を使った麺やパンなどが開発されています。
環境負荷が少ない

家畜として多種多様な動物が飼育されている中で温室効果ガスを多く排出するのは牛や羊などの反すう動物です。反すう動物が繊維質の高い飼料を食べると、それらを消化する過程でメタンガス(CH₄)を発生します。このメタンガスには、二酸化炭素(CO₂)の28倍の温室効果があります。昆虫を養殖することで発生するメタンガスは反すう動物の約100分の1程度[※5]なので、昆虫食の普及により温室効果ガスの削減が期待できるといわれています。
人獣共通感染症を媒介しない

人獣共通感染症(ズーノシス)とは、人間と人間以外の脊椎動物がかかる感染症のことです。人獣共通感染症というと耳馴染みがないかもしれませんが、狂犬病・トキソプラズマ症・エキノコックス症というと分かりやすいかと思います。病原体を媒介した脊椎動物と人間が接触したり、排泄物等を吸入してしまうことで感染します。無脊椎動物である昆虫はこの人獣共通感染症を媒介しないので感染リスクがありません。
昆虫食のデメリット
ここまで昆虫食が持続可能な食糧源として優れている点をご説明いたしましたが、デメリットもございます。1つずつ見ていきましょう。
食欲がそそられない

これは別の記事『昆虫食はなぜ気持ち悪いのか。嫌悪感の原因について考えてみた』に詳しく記載しているのですが、雑食動物である私たち人間には、これまで口にしたことがない食材を警戒する「食物新奇性恐怖」という習性があるといわれています。昆虫を食べる機会が少ない現環境で昆虫という食材は未知そのものであり、食物新奇性恐怖によって「食べたくない」という拒絶反応が出てしまうのです。また、先進国における昆虫は「駆除の対象」であり、もし飲食店で皿の上に乗った昆虫が提供されようものなら「異物混入」と捉えられてしまうかと思います。そこで登場したのが昆虫の姿が分からないように加工された食品です。弊社でも約100匹分のコオロギを配合した高たんぱくなカップ麺「コオロギうどん」を販売しています。
美味しさが鮮度に依存する

食肉には酵素による作用で旨味をアップする「熟成」という手法がありますが、不飽和脂肪酸を豊富に含む昆虫は魚介類と同じで酸化が進みやすい(傷みやすい)ため長期的な熟成には向きません。また、生きている状態であれば問題ないのですが、締めた昆虫が傷ついたり、時間が経過することでメラニゼーションという作用が起こり黒っぽく変色して見た目が悪くなります。もし野生の昆虫を食用として捕獲した際には、新鮮なうちに下ごしらえ(洗浄・加熱)を済ませて、水気をとったらジップロック等の空気を抜いて密封できる容器に移し、冷凍庫で保存しておくことをオススメします。
アレルギーのリスク

消費者が食品を安全に摂取し、自主的かつ合理的に選択するための「食品表示法」では、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品を「特定原材料」と定め食品表示が義務付けられていますが、この記事を執筆している2021年10月時点で昆虫は「特定原材料」に指定されていません。しかしながら、昆虫にはトロポミオシンというアレルゲンが含まれています。[※8]このトロポミオシンは甲殻類(エビ・カニ)にも含まれるもので、食物アレルギーを持つ人が口にしないよう注意しなければなりません。また、すべての食材に共通することにはなりますが、アレルギーを持たない方でも今まで食べたことのない食材を口にするという行為にはアレルギー発症のリスクが伴います。最初は少量ずつ、様子を見ながら食べるようにして、罰ゲームやサプライズ等に使用しないようにしましょう。
食中毒のリスク

他の野生動物(ジビエなど)にも言えることですが、野生動物は食中毒の原因となる寄生虫や病原菌の媒介者になることがあります。テレビやインターネットで生きた虫をそのまま食べるシーンを目にすることがありますが、これは食中毒を引き起こすかもしれない危険な行為です。絶対に真似をしないでください。野生の昆虫を食べる前にはしっかりと洗浄・加熱を行うようにしましょう。それと、あまり知られてないのですが、日本に生息する虫にも毒を持つものが存在します。その中でもとくに危険性が高いといわれているのは、猛毒カンタリジンを持つ「ツチハンミョウ科」や「カミキリモドキ科」の昆虫です。カンタリジンを摂取すると、吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、血尿などの症状が出るほか、わずか30mg程度で致死量に達してしまうので非常に危険です。種類を特定できない虫を捕まえても絶対に口にしないでください。なお、バグームの商品は食べられる昆虫だけを使用し、洗浄・加熱もしっかりと行っております。さらに、厚生労働省検疫所に食品等輸入届出書を提出し許可を受けた食品になりますので、安心してお召し上がりいただくことができます。
引用・参考文献
- ※1:『世界の昆虫食市場 2025 年に 1,000 億円規模に MDB Digital Search 有望市場予測レポートシリーズにて調査』,株式会社 日本能率協会総合研究所,http://search01.jmar.co.jp/static/mdbds/user/pdf/release_20201221.pdf,(参照2021-10-12)
- ※2:『Edible Insects – Future prospects for food and feed security』,国際連合食糧農業機関,http://www.fao.org/3/i3253e/i3253e.pdf,(参照2021-10-12)
- ※3:『昆虫の食糧保障、暮らし そして環境への貢献』,http://www.fao.org/3/i3264it/i3264it.pdf,(参照2021-10-12)
- ※4:『TEDx Talks, Why eating bugs will soon become the new normal | Jenny Josephs | TEDxSouthamptonUniversity,2015-7-21』,https://youtu.be/LgBlNDqVI94,(参照2021-10-12)
- ※5:Oonincx, D.G.A.B., van Itterbeeck, J., Heetkamp, M. J. W., van den Brand, H., van Loon,
J. & van Huis, 『An exploration on greenhouse gas and ammonia production by insect species suitable for animal or human consumption』,https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0014445,(参照2021-10-12) - ※6:『親子で学ぶちくさん|飼料・畜産情報』,ジェイエイ北九州くみあい飼料株式会社,http://www.jakks.jp/feed/prtprocess/beefcattle.html,(参照2021-10-12)
- ※7:三橋 淳,『昆虫食文化事典』, 初版第1刷発行, p112, (八坂書房)
- ※8:Reese G, Ayuso R, Lehrer SB. Tropomyosin: an invertebrate pan-allergen. Int Arch Allergy Immunol. 1999 Aug;119(4):247-58. doi: 10.1159/000024201. PMID: 10474029,(参照2021-10-12)