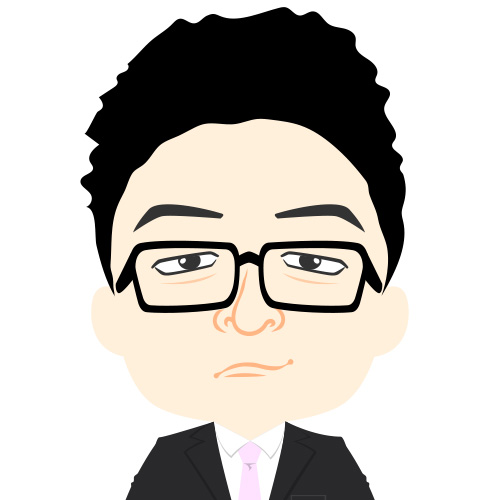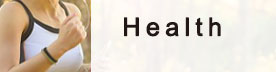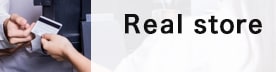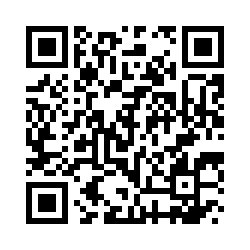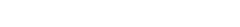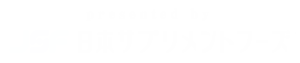【大名店】閉店のお知らせ
目次
昆虫食はなぜ気持ち悪いのか
昆虫食に乏しい私たち日本人が、虫を食べるなんて気持ち悪いと思ってしまうことは仕方のないことです。

例えば、日本の発酵食品の代表格である納豆。私たちには馴染み深い食材ですが、納豆を初めて目にした外国人の多くは「気持ちが悪い」と感じてしまうそうです。このことを心理学の世界では食物新奇性恐怖(しょくもつしんきせいきょうふ)といい、雑食性の人間が初めて口にするものを警戒するために備わっている習性だと考えられています。日本人が何の抵抗もなく納豆を食べることができるのは、幼い頃から当たり前のように納豆を食べてきたからでしょう。
但し、ここで1つ疑問が残ります。食物新奇性恐怖を引き起こすトリガー(不安要素)が単純に「食べたことないから」というだけなら、昆虫食が強く拒絶されることはないでしょう。考えてもみてください。普段から肉を食べていれば鹿や猪といったジビエ肉を食べたことがなくとも、それらを口に運ぶことはそう難しいことではないですよね。昆虫食だけが強く拒絶される理由には、昆虫食ならではのトリガーが隠されているはずです。
一体、どのようなトリガーが存在するのか、そしてそのトリガーはどのようにすれば取り除けるのかを考えてみました。
見た目のインパクト
虫を食材として見ることができない最大の理由は、きっとその見た目でしょう。頭から生えた長い触覚、独特の色や模様、数が多くて長い脚…こうした特徴を持つ食材がお皿に盛られていると、どうしても抵抗を感じてしまうものです。しかし、私たちが普段から口にしている食材の中にも、実は同じような特徴を持つものがあります。
それは、昆虫と同じ節足動物と呼ばれるグループに属する甲殻類です。

(↑エビ:長い触覚と、複数の脚が伸びている。体は硬い外骨格に覆われていて、胴体は特徴的な縞模様。)

(↑シャコ:長い触覚があり、頭胸節・胸節・腹節から複数の脚が伸びている。硬い外骨格を持ち、種類によって色や模様も違う)
どちらも昆虫に嫌悪感を抱く外見的な特徴を持っているにも関わらず、日本で古くから食べられてきた食材です。とくにエビは、お正月に食べる”おせち料理”の中に必ずと言っていいほど入っていますが、それを見て大騒ぎするような人はいないかと思います。虫を平気で食べられる人たちも、それと同じ感覚で食材として虫を見ているのです。
ちなみに余談ですが、バッタに火を通すとエビのように赤く染まります。風味自体もエビに似ているので、バッタは海老に慣れ親しんだ日本人向けの昆虫食かもしれません。
不衛生なイメージ
草木の少ない都会で見かける虫といえば、ゴキブリやハエといった不衛生な場所に住み着くものばかり。食事中にそれらの昆虫の名前を出すことはタブーとされ、飲食店では「〇番」などの隠語が使われることもあります。そんな環境で生活していると、虫に対して不衛生なイメージを持ってしまうのは仕方がありません。
ですがご安心ください。ゴキブリやハエなど細菌を媒介している可能性のある虫が、そのまま食用として流通するようなことはまずありません。
例えば、私たちが普段口にしている肉は、衛生的な環境で育った牛や豚、鶏の肉ですよね。同じ肉でも、不衛生な環境で飼育・加工された動物の肉が出回ることはないはずです。これと同じように、昆虫食の世界でも食べられる虫、食べてはいけない虫を見分けて、食用とするための適切な処理が行われた虫が流通しているのです。

また、昆虫食の製造工場は、医薬品に使用されている品質管理基準のGMPや、宇宙食の安全性を確保するために開発された衛生管理方式のHACCP、欧州で使われている商品の衛生基準BRCを採用しているところも多く、品質と安全性のレベルは高く保たれています。
健康へのリスク
百万種類を超える昆虫の中には毒を持つものも存在します。アニメや映画といったフィクションの世界では、大きな毒針を持つサソリや、毒蜘蛛と呼ばれるタランチュラが危険な生き物として描写されていることも多いです。こうしたイメージから「毒があるから食べられない」と考える方もいらっしゃいます。

けれど、実は致命的な毒を持つサソリは全体の2%程度。タランチュラにも人が命を落とすほどの強い毒はありません。さらに、彼らの毒は加熱によって失活するので、海外のマーケットでは当たり前のように素揚げや串焼きにされたものが並んでいます。
私たちが普段から食べている食材の中にもフグやオコゼ、カサゴなど毒を持った生き物が存在するわけですから、どんな食材も正しい知識を持って調理すれば食べられることは実証されています。それと同じように虫にも食べられるもの、食べられないもの、食べられるけど適切な下処理が必要ものがあって、市場には安心して食べられるものが出回っているのです。
なぜ気持ち悪い虫を食べるのか

昆虫食は、来る食料危機を救う存在として注目を集めていますが、今はまだまだ好きなものが食べられる飽食の時代。高いハードルを越えてまで虫を食べる理由はないと考える方が大半かと思います。
たしかにその通りで、先述したもの以外にも「安定供給の難しさ」や「調理バリエーションの乏しさ」など昆虫食のハードルとなる要素は他にも存在します。肉や魚に代わるタンパク源の1つとして期待されているものの、まだまだ手軽に取り入れるのは難しいというのが現状でしょう。
しかし、食を楽しむという意味では肉や魚に劣らない魅力があります。例えばイエコオロギは小ぶりながらもしっかりとした旨味があって、ゾウムシの幼虫であるサゴワームは油脂感のあるナッツのような濃厚なコクがあります。竹を食べて育つバンブーワームはミルキーな香りとマイルドな味わいが特徴的で、蚕は空豆のような風味があり乾燥品はザクっとしたクリスピー食感。こうした発見や感動は、この飽食の時代にはなかなか出会えない貴重なものだと思っています。
もしこの記事を読んで昆虫食に興味が湧いたという方は、この機会に昆虫食を召し上がってみませんか?これまでにないドキドキとワクワクを一緒に楽しみましょう。