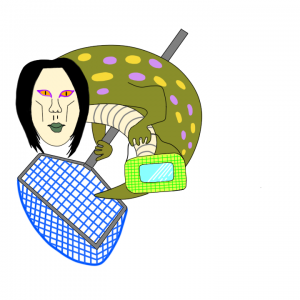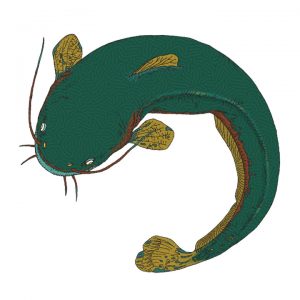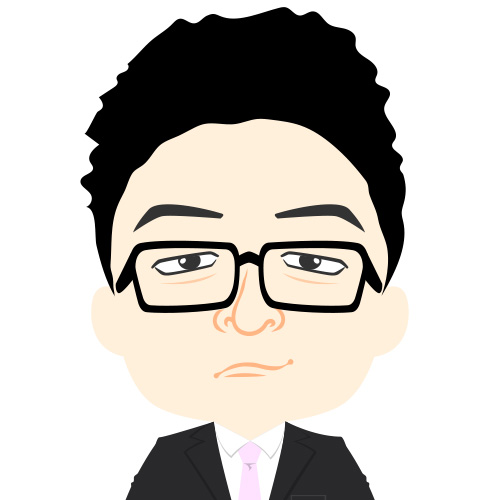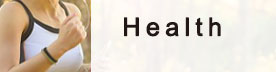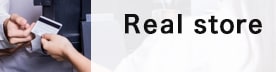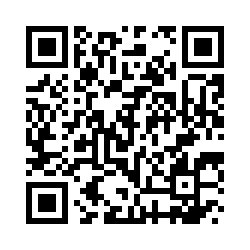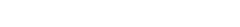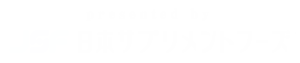【大名店】閉店のお知らせ
目次
知らないうちに虫を食べているかも
昆虫食の販売店をやっていると「虫を食べるなんて考えもしなかった」という声を耳にすることが多いです。たしかに、一般的な日本の食卓には「コオロギ」や「ミルワーム」が並ぶことはありません。でも実は、コンビニやスーパーで手に入る食材だけを食べていても、知らないうちに虫を口にしていることがあります。今回は、その一部をご紹介させていただきます。
食品添加物として
食品の品質を保ったり、色を付けたりするために使用する食品添加物の中には、昆虫を原料としているものがあります。
シュラック

シュラックとは、食品の光沢剤やコーティング剤として利用される添加物です。フルーツの光沢を出すために使用されたり、医薬品やお菓子をコーティングするために使用されています。その正体は、熱帯・亜熱帯に分布するカイガラムシの分泌物になります。これは虫体被覆物と呼ばれていて、カイガラムシが吸収できなかった栄養・排泄物です。常温では黄色または褐色ですが、精製すると白または透明になり、人体には無害であることが証明されていますので、ご安心ください。
コチニール色素

コチニール色素とは、食品に赤色を付けるために使用される着色料です。コチニール色素のほかに、カルミンレッドK、カルミンレッドMK-40、カルミンレッドKL-80、クリムゾンレーキ、ナチュラルレッド4[1]、C.I. 75470[1]、E120などの呼ばれ方もしています。主にジュースやお菓子、ウィンナーやベーコン、お酒などに使用されます。その正体は、なんとカイガラムシから抽出した色素になります。カイガラムシ…大活躍ですね。
銅クロロフィル

銅クロロフィルは、食品に緑色を付けるために使用される着色料です。主に抹茶風味のお菓子に使用されています。その正体は、桑の葉をモリモリ食べて成長する蚕(かいこ)の糞です。厳密には、蚕の糞から取り出したクロロフィル(葉緑素)と銅を結合させたものになります。お茶を入れられることでも知られる蚕の糞ですが、実は着色料としても活躍していたのです。
食品混入物として
私たちが口にすることの多い食材には、稀に昆虫たちが紛れ込むことがあります。
米

お米を主食とする私たち日本人は、貯穀害虫に悩まされてきました。貯穀害虫の中でも有名なのが米食い虫と呼ばれるコクゾウムシです。彼らは穀物に卵を産み付けて、幼虫は米を餌に成長していきます。色が黒い成虫はすぐに見分けることができるのですが、色が白い幼虫は見分けるのが難しく、知らず知らずのうちに口にしてしまっている可能性が高いです。ただ、ご安心ください。コクゾウムシは無毒なので食べても害はなく、近年は精米技術の向上により混入の可能性も低くなっているそうです。さらに、コクゾウムシは水に浮くので、慎重に米研ぎをすれば取り除くことも可能です。
ブロッコリー

高い栄養価を持ち、がん予防や糖尿病の改善にも役立つといわれているブロッコリーですが、葉の裏や蕾の隙間に虫が潜んでいる場合があります。小さなアブラムシやコナガ、1cmを超えるアオムシやヨトウムシなどその種類は様々です。いずれも口にしても問題のない昆虫ですが、気になる方はしっかり洗ってから茹でるようにしましょう。
米・粉・お菓子

家の中に備蓄している米や小麦粉、お菓子類に虫がつくことがあります。それらにつく虫の1つとして挙げられるのがノシメマダラメイガです。彼らは幼虫の時にお米やお菓子が大好物です。成虫になると何も食べなくなるのですが、夜行性でいながらも一般的な蛾のように光に集まるような習性はなく、暗闇を飛び回って繁殖を行います。米びつや開封したお菓子や小麦粉はしっかりと密閉してから保管するようにしましょう。
まとめ
普段、口にしている動植物が添加物の原料になっていても抵抗はないですし、貝の中に小さな蟹が紛れ込んでいるのを見つけたら「ラッキー」とすら思ってしまいますよね。しかし、それが虫となると一遍し「気持ち悪い」という認識に変わってしまいます。アメリカでは虫の食品混入に関する明確な基準(食品〇gに対して何匹以下であること等)がありますが、この日本で食品に少しでも虫が紛れ込んでいようものなら大きな騒ぎになり、それが加工食品であれば同じロットで製造された商品を全て回収するという事態に発展することも珍しくはありません。もしもこの先、昆虫食が一般的な食材として認められるようになれば、こうした認識も変わっていくのかもしれませんね。